江藤淳「南洲残影ー『ふるさとの驛』」
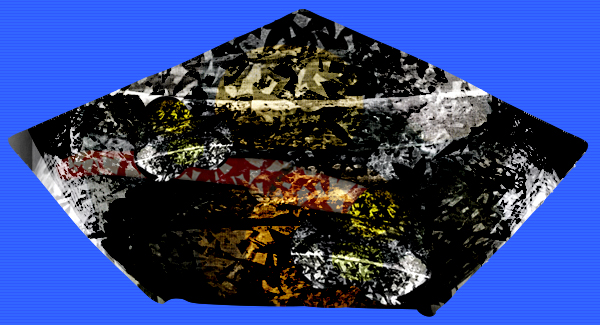
記念碑に向かって左手に、散歩道のような小径が設けられて、紅白の提灯が沿道を彩っている。何の気なしに、その小径を行きかけて、ふと見ると、意外なものが目にとまった。「蓮田善明先生文学碑」と刻された、小さな石柱であった。文学碑そのものは、高さ三尺ほどの自然石の側面を削って、一首の短歌を彫りつけた簡素な碑である。
ふるさとの 驛におりたち
眺めたる かの薄紅葉
忘らえなくに
と読める。
そうか、この地は蓮田善明の「ふるさと」だったのかと、私は一瞬哀切な想いに胸を衝かれた。それにしてもこれは、なんとあえかな歌ではないか。そしてまた、なんとつつましやかな文学碑ではないか。
ここには高度成長期に簇出した諸家の文学碑の周辺に漂う。ふんぷんたる俗臭ごときものはいささかもない。ふるさとびとが相集って、非命に斃れた詩人の記憶を後世に伝えようとしたという志が、ほのかに香るような歌碑である。
言うまでもなく、蓮田善明は、「文藝文化」の編集名義人だった国文学者にほかならない。この地植木町の金蓮寺住職の三男として生まれ、広島高師から広島文理大に進んで、正常高校で教鞭を執った。その頃、昭和十三年七月に創刊されたのが、国文学研究誌でもあり文芸雑誌でもある「文藝文化」である。
ー略ー
昭和十三年応召し、中支に転戦したが、戦傷を受けて十五年歳末に帰還、この間も塹壕のなかから詩歌、随想などを「文藝文化」に寄稿しつづけた。
昭和十八年十月、再び召集されて陸軍中尉として南方戦線に派遣され、マレー半島のジョホールバルで終戦を迎えた。その直後、聯隊長を利敵行為の故を以て射殺し、同じピストルで自裁した。享年四十一、昭和二十年八月十九日のことである。
学習院中等科の生徒だった三島由紀夫を見出し、「花ざかりの森」を「文藝文化」に連載したのは、蓮田善明である。その第一回が掲載された第三十九号の編集後記に、蓮田は記している。
《「花ざかりの森」の作者は全くの年少者である。どういふ人であるかといふことは暫く秘しておきたい。それが最もいいと信ずるからである。…この年少の作者は、併し悠久な日本の歴史の請(ママ)し子である。我々より歳は遥かに少ないがすでに成熟したものの誕生である》
ときに三島は十六歳、この後記は、作家三島由紀夫と日本浪曼派との絆の深さを物語るものとして、従来から重要な証言とされている。…
そのようなことを想いながら、蓮田善明の文学碑の前に立ちつくしているうちに、雨が上がってきた。左手の谷間を眺めると、桜の蕾が色づきはじめているのが見わたせる。ところで、植木町が蓮田の「ふるだと」だとしても、何故この碑は田原坂の古戦場に建っているのだろう。「烈火の如き談論風発ぶり」(三島由紀夫『文藝文化』のころ)を謳われた蓮田の文学が、何故「ふるさとの驛」の「かの薄紅葉」という表象によって要約されているのだろう。
そう自問したとき、一種電光のような戦慄が身内を走った。西郷隆盛と蓮田善明と三島由紀夫と、この三者をつなぐものこそ、蓮田の歌碑に刻まれた三十一文字の調べなのではないか。西郷の挙兵も、蓮田や三島の自裁も、みないくばくかは「ふるさとの驛」の、「かの薄紅葉」のためだったのではないだろうか。
滅亡を知る者の調べとは、もとより勇壮な調べではなく、悲壮な調べですらない。それはかそけく、軽く、優にやさしい調べでなければならない。何故なら、そういう調べだけが、滅亡を知りつつ滅びていく者たちの心を歌い得るからだ。
蓮田善明その人と、蓮田の歌を碑に刻んだふるさとびとたちが、交々にそう語りかけて来るように思われた。田原坂の空間には、明治十年の西南の役の時間が湛えられているだけではなかった。この時空間には、昭和二十年の時間も昭和四十五年の時間も、ともに湛えられてめぐり来る桜の開花を待っていた。
江藤淳「南洲残影〜『ふるさとの驛』」

