夢のなごり・1
夢のなごり・2
夢のなごり・3
夢のなごり・4
夢のなごり・5
夢のなごり・6
夢のなごり・7
夢のなごり・8
夢のなごり・9
夢のなごり・10
夢のなごり・11
夢のなごり・12
夢のなごり・13
夢のなごり・14
夢のなごり・15
夢のなごり・16
夢のなごり・17
archive
失はれた雲を求めて
神々の夢のなごり・Jamais de la vie
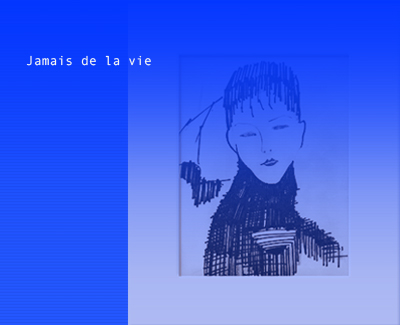
月の光のしずかにすべりゆくとき、想ひがすべてのうへに在るとき、我が目には波はうなばらと映らず、森は樹々のあつまりとはみえず、天空をかざるは雲にあらず、峪や丘はもはや地のおきふしとはみえず、うつし世はうたかたの如、すべては神々のみたまふ夢のなごりなり。 シェーンベルク : Gurre-Lieder
![]()
2024.07.28「雪万家」
以前、三好達治の有名な詩「雪」を作品にしたが、出来は今一つ。何時か書き直さうと思つてゐたが、果たせぬ儘、今日に到つてしまつた。やうやく新たに描きなおす準備を始めたが、体調も悪く、パソコンを凝視して、目を酷使せねばならぬことを考へると、気力が失せてきた。さういふわけで、テキストとして採用を予定してゐた、山本健吉先生の「蕪村の画と俳意」を先にご紹介して、作品制作は先送りしたい。
「私にとって蕪村の画について語ることは、何よりもまず《夜色楼台雪万家図》について語ることだ。
ー略ー
そして《夜色楼台雪万家図》は、私には図抜けて蕪村の個性の現れた秀作と思われる。私はまずこの画について語りたい。
この画にははるか後になって、一人の日本の詩人が、ひそかに賛を書いていた。
雪 三好達治
太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ
次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ
あるとき、達治門と言ってもよい俳人の石原八束君が、私の家に来たとき、ふと洩らしたことがある。
『三好さんは、あの詩は、蕪村の画に《夜色楼台雪万家図》というのがあるでしょう。あれだって言うんですよ』
この一言は、たちまち私にさまざまの感想をもたらした。私は東山とおぼしい連山の上に、垂れこめた暗鬱な雪空のもと、雪に閉ざされた京洛の町の家々の屋根がびっしりと書きこまれ、その中にいくつかの楼台が高くそびえ、うすい燈りが灯されている、あの横長の図面をぼんやりと憶いだしていた。あの画が三好氏の心中にあったというのは、この詩が作られた時ではなく、後から氏の心の中に、画と詩が相互補足するような形で寓(やど)るに到ったのではないかと思う」
ー以下略ー
山本健吉「蕪村の画と俳意」
解釈といふ程のものではないが、私の感想を言ふと、太郎次郎を眠らせるのは雪である。雪は農作物の豊穣を齎し、子供を安らかな眠りにさそふ神である。
この詩を鑑賞するにあたつては、人それぞれでいいが、ここに参考になりさうな文章があるので、ご紹介したい。
「この作品は、同一行内での「太郎」のくり返しを梃子にして、俳句の方で言ふ『二物とりり合はせ』の方法と、『一物にて作す』方法との、微妙な境ひ目に成り立ってゐると思はれる。『太郎』のくり返しによって、行の前半と後半の『切れ』に注目すれば、人事と自然、屋内と屋外の対比ともなり、『雪』を主語と意識すれば、全体が一つに融け合ふのである。この微妙なバランスの揺れにしたがって、読者の中に、さまざまな方向に向ふ連想の糸がつむがれ始め、読者それぞれの『体験』『経験』が自由にくみ入れられて行く。
この詩は、元来がさういふ豊かさを、構造的に内に包み持ってゐる詩であり、逆に言って、それだからこそ、多くの人々によって、多様な、しかもそれぞれに豊かな受容を可能にしてゐるのだ」
入沢康夫「太郎を眠らせ…」

2024.05.28「パクス・ロマーナ」
「キケロからマルクス・アウレリアスまでのあいだ、神々はもはやなく、キリストは未だいない、ひとりの人間のみが在る比類なき時期があった」
フロベールの云ふ「比類なき時代」とは、どんな時代だつたのか。ここは、塩野七生著「ローマ人の物語 Ⅸ」から引用させて戴く。
「アントニヌス・ピウスの治世の五年目、つまりハドリアヌスの死後五年目にあたる紀元一四三年に、四月二一日のローマ建国祭に招かれた小アジア生まれの哲学者のアエリウス・アリスティディスは、皇帝アントニヌスと並居る元老院議員を前にして、公演を行った。その一部を紹介したい。
『今や、わたしのようなギリシア人にとって、いや他のどの民族にとっても、行きたいと思う地方に旅することは、身分を証明する書類の申請さえも必要としないで実行できる、自由で安全で容易なものになっている。ローマ市民権の所有者であるだけで、充分になったのだ。いや、ローマ市民である必要さえもない。ローマの覇権の許で、ともに暮す人であるというだけで、自由と安全は保証されているのだ。
かって、ホメロスは謳った。地上はすべての人のものである、と。ローマは、詩人のこの夢を、現実にしたのである。あなた方ローマ人は、傘下に収めた土地のすべてを、測量し記録した。そしてその後で、河川には橋をかけ、平地はもちろんのこと山地にさえも街道を敷設し、帝国のどの地方に住まおうと、行き来が容易になるように整備したのである。しかもそのうえ、帝国全域の安全のための防衛体制を確立し、人種がちがおうと民族を異にしようと共に生きていくための法律を整備した。これらのことすべてによって、あなた方ローマ人は、ローマ市民でない人々にも、秩序ある安定した社会に生きることの重要さを教えたのであった』。」
2024.04.19「橋をかける」
小林秀雄先生と同様、普段私も天皇にアンティミテ(親しみとでも訳すのか)を感じてゐるわけではないが、日本に生まれ日本で育つた人間である。心の何処かに天皇が存在してゐるのに違ひない。皇統が二千年もの間、連綿と続いてゐるからには、それは日本人が自ら選びとつた歴史、伝統と言へるだらう。
「執行草舟の視線」 竹本忠雄
「日本には日本的方法、すなわち偉大な霊性文化があるのに、それを見失ってしまったことに、われわれの悲劇はあった。ルーツ喪失…この一言に尽る。
では、滅却された我らのルーツとは何であったか。戦後、これを至上の高みで啓示した二人の偉人があった。三島由紀夫と平成の御代の皇后陛下美智子さまである。
三島由紀夫の理念は最後の檄文の結びにこう凝縮されている。
『生命尊重以上の価値の所在…それは自由でも民主主義でもない。日本だ。われわれの愛する歴史と伝統の國、日本だ』
愛することと殉ずることは一なることを、こう訴えた直後に取った自刃の行為によって、三島は実証した。
これと同日に論ずることは懼れ多いことながら、皇后美智子さまは、この上ない高みから、この上ない透明な光を日本的霊性の源泉の上に投げられた。一世の名講演、「橋をかける」において弟橘比売命の相模湾入水の歌を引いて、こう仰せられた点である。
『《いけにえ》という、酷い運命を、進んで自らに受け入れながら、恐らくはこれまでの人生で、最も愛と感謝に満たされた瞬間の思い出を歌っていることに、感銘という以上に、強い衝撃を受けました。(…)愛と犠牲という二つのものが私の中で最も近いものとして、むしろ一つのものとして感じられた、不思議な経験であったと思います』
さらに『愛と犠牲との不可分性への、恐れであり、畏怖であった』として、捨身におけるサクレ(聖性)的性質に触れておられる。
この述懐に先立って美智子さまは、戦後、米軍の占領下で歴史教育から神話や伝統が削除されたことによって『民族の共通の祖先』の『一つの根っこのようなもの』が失われてしまったことを嘆いておられるのである。
平成八年歌会始 御題 終戦記念日
海陸のいづへを知らず姿なきあまたの御霊國護るらむ 皇后陛下御製
美智子さま御著書「橋をかける…子供時代の読書の思い出」より
「父のくれた古代の物語の中で、一つ忘れられない話がありました。
年代の確定出来ない、六世紀以前の一人の皇子の物語です。倭健御子と呼ばれるこの皇子は、父天皇の命を受け、遠隔の反乱の地に赴いては、これを平定して凱旋するのですが、あたかもその皇子の力を恐れているかのように、天皇は新たな任務を命じ、皇子に平穏な休息を与えません。悲しい心を抱き、皇子は結局はこれが最後となる遠征に出かけます。途中、海が荒れ、皇子の船は航路を閉ざされます。この時、付き添っていた后、弟橘媛命は、自分が海に入り海神のいかりを鎮めるので、皇子はその使命を遂行し覆奏してほしい、と云い入水し、皇子の船を目的地に向かわせます。この時、弟橘は、美しい別れの歌を歌います。
さねさし相武の小野に燃ゆる火の火中に立ちて問ひし君はも
このしばらく前、健と弟橘とは、広い枯野を通っていた時に、敵の謀に会って草に火を放たれ、燃える火に追われて逃げまどい、九死に一生を得たのでした。弟橘の歌は「あの時、燃えさかる火の中で、私の安否を気遣って下さった君よ」という、危急の折に皇子の示した、優しい庇護の気遣いに対する感謝の気持を歌ったものです。
悲しい「いけにえ」の物語は、それまでも幾つかは知っていました。しかし、この物語の犠牲は、少し違っていました。弟橘の言動には、何と表現したらよいか、健と任務を分かち合うような、どこか意志的なものが感じられ、弟橘の歌は、あまりにも美しいものに思われました。「いけにえ」という、酷い運命を、進んで自らに受け入れながら、恐らくはこれまでの人生で、最も愛と感謝に満たされた瞬間の思い出を歌っていることに、感銘という以上に、強い衝撃を受けました。はっきりとした言葉にならないまでも、愛と犠牲という二つのものが、私の中で最も近いものとして、むしろ一つのものとして感じられた、不思議な経験であったと思います。
この物語は、その美しさの故に私を深くひきつけましたが、同時に、説明のつかない不安感で威圧するものでもありました。
古代ではない現代に、海を静めるためや、洪水を防ぐために、一人の人間の生命が求められるとは、まず考えられないことです。ですから、人身御供というそのことを、私が恐れるはずはありません。しかし、弟橘の物語には、何かもっと現代にも通じる象徴性があるように感じられ、そのことが私を息苦しくさせていました。今思うと、それは愛というものが、時として過酷な形をとるものなのかも知れないという、やはり先に述べた愛と犠牲の不可分性への、恐れであり、畏怖であったように思います」
2024.03.23「戦いの文化」
「わたしの母が、ある時、台所で漬物を刻みながら、突然、
『チャガタイ、オゴタイ、イル、キプチャク』
と唱うようにいったから私は魂消た。
人間の記憶というのは、まことにもって気まぐれなものではないか。六十何歳にもなって、突如、女学校時代の歴史の勉強の断片が浮かび上がってくる。ホラ、あなたもおぼえてないかな、チャガタイ汗国、オゴタイ汗国、イル汗国、キプチャク汗国」
伊丹十三「再び女たちよ!」
チンギス・ハーンの長子一族が興した「キプチャク汗国」は、黒海の北、現在のロシア、ウクライナ一帯を支配した。住民は過酷な支配と重税に苦しみ、これを「タタールの軛」とよんだ。現在のロシアは、軛から辛うじて独立した「モスクワ大公国」を淵源とする。
帝政ロシアに生まれ、ソ連で成長し、最後はロシア人としてモスクワで亡くなった、ピアニストのリヒテルは言ふ。
「私が生を享けた町ジトミルは今で言うウクライナにありますが、私の生まれた1915年にはウクライナは存在せずロシアでした。『小ロシア』です。父方の祖父は、今日ではウクライナ西部になりますが、当時はポーランド領だったブレゼーニャ出身のドイツ人でした。運試しにロシアにやってきた多くのドイツ人に倣って、祖父は前世紀の中頃、ピアノ職人としてジトミルに住み着きました。父はそこで生まれました」 (リヒテルの母上はロシア人)
ブリューノ・モンサンジョン「リヒテル」
リヒテルの年下の友人、ボリゾフのは言ふ。
「リヒテルは、丁寧に折りたたんだ紙を差し出した。予定表だった。練習と散歩、夕刻の演奏会、夜間の訪問が記されていた。ここはキエフ。彼はこの、『ロシアの母なる町』での公演を目前に控えていた」
ユーリ・ボリゾフ「リヒテルは語る」
キエフがロシアの母なる町?。
そう言へば、ロシア人であるムソルグスキー作曲『展覧会の絵』のなかに、『キエフの大門』といふ曲があつた。
ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド辺りは、時代とともに各国の国境が動き町の名が変つて、私には解りづらい。
2022年2月、ロシアがウクライナを侵略してから略2年。
折しも、3月23日付け産経新聞に、エドワード・ルトワック氏の興味深い論説が掲載されてゐた。曰く、「欧州は戦いの文化を取り戻せ」。以下、引用する。
「ウクライナの戦況は日々悪化している。ウクライナで自ら戦おうとする機運が国民全体に広がらず兵員不足に陥っているからだ。問題の一つは徴兵制だ。欧州諸国では対象年齢の下限が18歳なのに、ウクライナでは27歳に設定されている。ウクライナ政府は年齢の下限を25歳に引き下げようとするが、反対に遭って実現できていない。今後、兵員不足が一層深刻化し、同国の配色が濃くなるのは避けがたい。
欧州では昔から戦争が頻発し、濃密な『戦いの文化』があった。エリート層の間では軍事的才能と勇気が尊重されてきた。だが、こうした文化は欧州の多くの国々で今や完全に死滅した。
ー略ー
ロシアに隣接する北欧諸国は『戦いの文化』を失わず、徴兵制を維持してロシアとにらみ合う。北欧諸国は仮に近隣のバルト三国がロシアに侵攻された場合、駆け付けて露軍と戦う用意と覚悟ができている。だが、ドイツやイタリア、スペインといった国では誰も徴兵制について語らず、ウクライナ派兵にも否定的だ。
米陸軍の総兵力は約45万人と第2次世界大戦後で最小の規模にある。欧州の協力抜きの作戦計画は非現実的だ。一方、英国はロシアへの強硬姿勢を堅持し、既に少人数の英軍要因をウクライナに派遣している。将来の有事に備えた『市民軍』の編成も議論されている。そして何より欧州の安全保障を脅かすという実害を起こしている『ポスト・ヒロイック』の文化を転換させるため、世論を喚起することが必要だ。
『戦いの文化』を維持するプーチン体制の攻勢にさらされるウクライナに残された時間は少ない。そして欧州も目を覚ます必要がある。第一次世界大戦後の間違った戦争忌避志向がヒトラー率いるナチス・ドイツの台頭を許した歴史を繰り返してはならない」
2024.02.11「身はいかならんとも」
小林秀雄講演[第一巻・文学の雑感]の学生との質疑応答で、天皇についての件がある。学生が小林先生に問ふ。
「われわれは天皇に対して、どのように接したらいいでしょうか」
それに対して先生は、
「君はどうして、そういう抽象的な質問をするのかなあ」と言ひ、さらに「君、天皇に関心あるの」と聞く。
政治問題としての天皇制に対する、今のインテリ風の解釈など、何も興味がないと言ひ切り、深夜、陛下御一人で行はれる新嘗祭の儀式、篝火の下で白酒黒酒、それに鴨の雑炊をいただきながら待つてゐる臣下に話が及ぶ。「普段僕は、天皇にアンティミテを感じないが、こういふ事がアンティミテといふものかと思つた」とも。そして、「日本という国、あるいは天皇というものについて、非常に卑俗なところから経験するんです」と答へられた。
そこから、昭和四十三年落成した皇居新宮殿を先生が拝見した話になつてゆく。故三島由紀夫は、「新宮殿には鬼がゐない」と発言したが、小林先生の話では、あれは陛下の事務所、仕事場だとのことだから、鬼はゐなくてあたりまへ、陛下の住まひは別にある。
昭和三十五年二月、アンドレ・マルローは昭和天皇に拝謁した。
奈良に行ってこられたそうですね。
さようでございます、陛下。
それはいいことをなさいました。なぜ、いにしえの日本に興味をお持ちですか。
武士道を興した民族が、騎士道を興した民族にとって、どうして無意味なはずがございましょうか。
しばし、間。天皇は、またも絨毯に視線を落としておられたが、
ああ、そう…あなたがこの国に来られてまだ間もないということもあるでしょうけれど、しかしあなたは、日本に来られてから、武士道のことを考えさせるようなものをひとつでも見たことがありますか?たったひとつでも。
質問は、縉紳の広間のなかに、あたかも古池に投じられた小石のひろげるような波紋を、絶望的なかたちで押しひろげていった。
竹本忠雄「マルロー 日本への証言」
陛下の御下問に対するマルローの返答は書かれてゐないが、絶望には及ばない。昭和二十年、八月十四日に陛下の終戦の御聖断があり、次の歌を詠まれた。
「爆撃にたふれゆく民の上をおもひいくさとめけり身はいかならんとも」
昭和天皇はマッカーサーを、終戦の年の九月二十七日に訪問し、会談された。その内容は明らかにされていない。というのは「天皇・マッカーサー会談」は、今後とも一切外部に洩らさない、という約疎句の下に行われたからである。
会談の内容は外務省がまとめて天皇に届けられた。通常この種の文書は、天皇が閲読した後で侍従長にわたされるのが慣例だが、天皇はマッカーサーとの約束を守られて、、これをそのまま手許に留められたままである。だだ藤田侍従長はそれを一読し、天皇は次の意味のことをマッカーサーに伝えたと記している。
「敗戦に至った戦争の、いろいろの責任が追求されているが、責任は全て私にある。文武百官は私の任命する所だから、彼らに責任はない。私の一身は、どうなろうと構わない。私はあなたにお委せする。この上は、どうか国民が生活に困らぬよう、連合国の援助をお願いしたい」 「侍従長の回想」
「私は大きな感動に揺すぶられた。死をともなうほどの責任、それも私の知り尽くしている諸事実に照らして、明らかに天皇に帰すべきではない責任を引き受けようとする、この勇気に満ちた態度は、私の骨の髄までも揺り動かした」
「マッカーサー回想記」
皇統は「日本国民といふ有機体の個性です。不合理だからやめるといふわけには参らぬ」小林秀雄
