久世光彦「帝都の詩人たちー『花筐』」
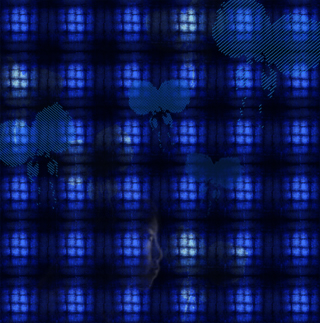
いつの日か、「花筐」というタイトルの本を世に出したいという願いを抱くようになったのは、いったいいつごろからだったろう。
―略―
何よりも、<花筐>という言葉は、美しい言葉だった。口にして香り高く円やかで、字に書いて、辺りに春霞が漂うように美しかった。たぶん<花筐>は、私が知っている日本の言葉の中で、五本の指に入るくらい、典雅な夢に誘ってくれる言葉なのである。もちろんそれは、三好達治が昭和十九年に上梓した詩集『花筐』に負うところが多い。そこに収められた詩篇―中でも四行詩の数々に、十代半ばだった私は心を奪われた。
青くつめたき石のへに/春のゆく日をあそびける/われらが肩にこぼれしは/花ともあらぬ柿の花
かへる日もなきいにしへを/こはつゆ艸の花のいろ/はるかなるものみな青し/海の青はた空の青
あはれしるをさなごころに/ありなしのゆめをかたりて/あまき香にさきし木蓮/その花の散りしをわすれず
ー略ー
二十歳を過ぎて、もう一つの「花筐」と出会った。昭和十二年に発表された檀一雄の最初の創作集だった。
ー略ー
「花筐」は、もともと世阿弥の狂女物の一つである。
ー略ー
もう彼らについて、あるいは彼らの狂乱の日々について書くことはないだろう。五十年にも及ぶ長い歳月の間、私の中に燻っていた<詩>への恋情は、書きおわったいま、嘘のように消えてしまったようだ。――これから足音もなくやってくるのは、<死>と親しむ季節である。
久世光彦「花筐」あとがき


notes15
gallery15