山本周五郎「『青べか物語』・芦の中の一夜」
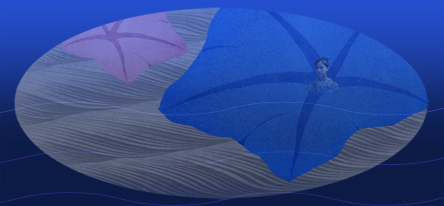
根戸川に沿った永島というところの、かなりな資産家だったそうで、その結婚が迫った或る日、娘は幸山船長としめし合わせ、東の浜の松並木でひそかに逢った。娘は持ってきた人形箱を渡し、体は嫁にゆくが自分の心はこの人形にこめてある、どうかこれを私だと思って持っていてくれ。そう云って泣いた。
娘の婚家は根戸川に近いので、幸山船長の乗った船が通ると、彼女は土堤まで出てきて姿を見せた。通船の排気音やエンジンの音は、それぞれに特徴があって、馴れた耳で聞くと何号船かということが判別できるという。娘は十七号船の音が遠くからわかるのだろう。ときにはあねさまかぶりに襷をかけ、裾を端折ったままで、たぶん洗濯なんかしていたのだろうが、あたふたと土堤へ駆けだして来たりする。出てきても手を振るとか声をかけるなどということはない、舟のほうを見るようすもなく、ただ船の通り過ぎるあいだ、自分がそこにいることを彼に見せ、また、さあらぬ態で彼のほうをひそかに見るのであった。川を遡航する時間は長くて五分くらいだし、くだりのときは三分たらずであるが、その水上と土堤との短くはかない、けれども誰にも気づかれることのない愛の交換は、若い彼にとってこの世のものとは思えないほどのよろこびであった。
やがて十七号船は荷物専用になり、彼は十九号船に移った。そのあいだに一度、五十日あまり彼女が姿を見せなかったことがあった。もうこれで終わりだろうか、娘の気持ちはさめてしまったのだろうか。彼は二人の仲を裂かれたときよりも激しい不安と、絶望感におそわれた。だがそれは思いすごしで、彼女はそのあいだ産褥についていたのだ、ということがわかった。再び土堤へ姿を見せたとき、彼女はおくるみで包んだ赤子を抱いていた。
「おかしなことだが」と幸山船長は云った、「まったく根もねえ話だが、そのときおらあ、あのこが抱いているのはおらの子だっていう気がしたっけだ、あの子がおらの子を生んだ、いま抱いているのはおらたち二人の子だってよ、先生なんぞにゃばかげて聞こえるかもしれねえだがね」
彼女の生んだのは女の子であった。彼は二十七歳でエンジナーになり、結婚した。妻は息子と娘を生み、三十二歳で死んだが、死なれるまで彼は愛情というものを感じたことがなかった。
彼は三十五で船長になった。水上と土堤との三百メートルの逢曳きは続いていたのだ。むろんずっとではない、どちらかの都合で相当な期間、お互いに姿を見ないこともあった。そのあいだに彼女は三児の母となり、彼のほうでは妻に死なれた。けれども、実生活の煩瑣な用事に邪魔をされながら、そうすることができる限りは姿を見せあった。二人はそれ以上に出ようとはしなかった。彼は永島へは近よったこともない、彼女が長く姿を見せないとき、病気ではないかと心を痛める。本当に病気だったこともあり、誰からともなく噂が耳にはいると、ようすをみにゆきたい、という抑えがたい衝動に駆られたものだ。しかし彼は、自分の中にある自分以上に強いなにかの力によって、そういう激しい衝動をきりぬけることができた。
「それでもたった一度だけ、側へよって口をきいたことがあるだよ」幸山船長は舵輪に凭れかかり、そっと頬笑んでいるような調子で続けた、「あれはそうさな、うちのおっかあが死ぬちょっとめえだっけかな、あのこが子供を伴れて、徳行からおらの舟へ乗っただ、伴れているのは四つくれえの女の子で、おらあその子を抱いて渡り板を船まで渡してやっただ、あのこはあとから渡って、子供を抱き取りながら、すみませんねえって云った、おらも云っただ、いまでも覚えてるだが、今日はいいお日なみですねってよ」
幸山船長は口をつぐみ、岸の松林のほうをじっと見まもっていた。
「すみませんねえ」と船長は呟き声で繰返した、「今日はいいお日なみですね」
彼が四十二の年に、彼女は死んだ。
それを知ったのは、六十日の余もあとのことであった。そのくらい姿を見せないことは幾たびもあったので、彼はかくべつ心配もしなかった。そして、彼女が六十日もまえに病死したと聞いたとき、ちょっと云いようのない感動に包まれた。悲しいことは紛れもなく悲しかった。この世では二度と逢えないと思うと、舵輪を握る気力もなくなり、五日だか七日だか休んで家にこもっていた。けれども、悲しさや絶望感の中に、一種ほっとしたような、うれしいような気分がうまれていた。
「どう云ったらいいか」と幸山船長は凭れている舵輪を指で撫で、暫く口ごもっていてから云った、「そうさな、あのこは死んでおらのとけへ戻って来た、っていうふうな気持ちだな、長えこと人に貸しといたものが返って来た、そんな気持だっけだ、おらそれから、人形箱の埃を払っただよ」
彼女は嫁にゆくが、心はその人形にこめてあると云った。彼はいまこそそれが現実になった、というように感じられたのだ。


notes10
gallery10