江藤淳「幼年時代」
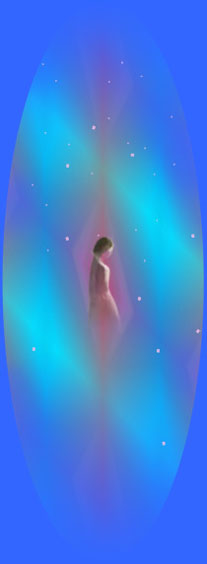
四通のなかで一番日付の旧いこの手紙を読み終わったとき、私は何とも名状しがたい想念がこみ上げて来るのを抑えることができなかった。
自分のことを他人事のように、へえ、そうか、やっぱりそうだったのかと、はじめて生みの母の筆で知らされるという驚きと喜びと哀しさが、胸に溢れないはずはない。しかし、それにも増して意外だったのは、この手紙の行間から、母の声が聴こえてきたという事実である。
何度読み返しても、いや、読み返すたびにその声は、私の耳の奥に聴こえてきた。それは落ち着いていて、知的で優しく、明るい張りのある声であった。わたしはもう、母の声をよく覚えていないなどとはいえない。手紙を 読み返すたびに、それは甦ってくる。読み返さなくとも、私はその声を忘れることなどできない。私は、母の声を知らない子ではなかったのである。
notes9
gallery9

