泉鏡花「蓑谷」
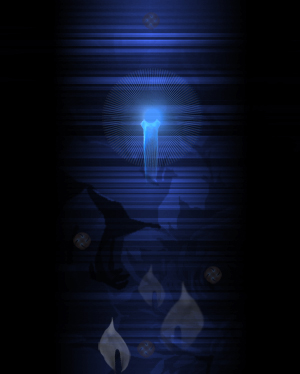
見るから膚の粟立ッばかり涼しげなる瀑に面して、背を此方に向けたるは、惟ふに彼の怪しの姫なるべし。
蓑谷の螢には主ありて、みだりに人の狩るをゆるし給はず。主といふは美しき女神にておはすよし、母のつねに語り給ひぬ。
谷をのぼれば丘にして、舊城のありたるあとなり。下は一面の廣野にて、笹川といふ小川其あひだを横ぎり流る。
はじめは其廣野にて、ともだちと連れなりしが、螢一ツ追ひかけて、うかうかと迷ひ來つ。野に居たりし時ハヤ人顔の懐しきまで黄昏れたりしを、樹立彌が上に生茂りて、空の色も見えわかざる、谷の色は暗かりき。
地も、岩も、木も草も、冷き水の匂ひして、肩胸のあたり打しめり、身を動かす毎にかさかさと鳴るは、幾年か積れる朽葉の、なほ土にもならであるなり。
瀑は樹と樹の茂り累なる梢より落つと見えぬ。半ばより岩にかゝりて三段になりて流る。左の方に小さき堂あり。横縦に鳶かづらのからみたるを、犇と封じて鎖を下せり。岩にせかるゝ瀑の雫、颯と其堂の屋根に灌ぎ、朽目を洩れて、地の上に滴りたり。傍 に一尺より二尺までの大きさの地藏尊、右の方を頭となし、次は次より次第に小さきが、一ならび
に七體ぞ立たせ給ふ。たゞ瀑のみならず、岩よりも土よりも水ところどころ湧き出づれば、此處彼處に溜りたる清水溢れて、小石のあはひを枝うちつゝ、白き蛇 のひらめくやう、低きに就きて流るゝ音、ものゝ囁くに異らざるを、鬱蒼たる樹立の枝を組みて、茂深く包みたれば、きく耳には恰も御佛達その腹の中にて、ものをいふらむ響す。
かゝる處に、身に添へる影もなくて唯一人立ちたる婦人の、髪も見馴れざる結方なり。黄昏の色と際立ちて、領の色白くあざやかに、曙 の蒼き色の、いと薄き衣着たまへる、ふみそろへたる足のあたりは、くらき色に蔽はれて、淡き煙、其帯して膨かなる胸を籠め、肩のあたりのさやかに見えて、すらりと立てる痩がたの身丈よく、ならびたる七つの地藏
の最も高きものゝ頭さへ、やうやく其胸に達するのみ、これを彼の女神ならずと誰か見るべき。
予が追來りたる一ツの螢の、さきよりしばし木隠れて、夕の色に紛れしが、蒼き光 明かに、彼の小さき堂の屋根に顯れつ。横さまに低く流るゝ如く、地藏の頤 のあたりを掠めて、うるはしき姫の後姿の背の半ばに留まりぬ。
「あゝ、」 姫なる神よ、其螢たまはずやといはむとせし、其言いまだ口を出でざるに、彼の君あわたゞしう此方を見向き、小さき予が姿を透し見ざま、驚きたる状して、一足衝とすさるとて、瀑を其頭にあびたり。左右の肩に颯と音して、玉の簾ゆらゆらとぞ全身
を包みたる。
「螢、下さいな、螢下さいな」
と予は恐氣もなく前に進みぬ。
螢は彼の君の脇を潛りて、いま袖裏より這ひ出でつゝ、徐 に其襟を這ふ時、青き光ひたひたと、ぬれまとうたる衣を通して、眞白き乳房すきて見えたり。
鼻高う、眉あざやかに、雪の如き顔 の、やゝおもながなるが、此方を瞻りたまへば、
「ねえ、螢 一ツ下さいな。母樣は然ういツたけれど。あの、神樣が大事にして居るんだから取ツちやいけないツて、さういつたけれど欲いんだもの、一ツ位いゝでせう」
と甘ゆる如くいひかけつゝ、姫の身近に立寄るに、彼の君はなほものいはで、予が顔を瞻めたまふ。目の色の見ゆるまで、螢の光凄く冴えたり。予は少しく恐氣立ちぬ。其姿の優しければこそ、來るまじき處に來て、神の稜威を犯せしを、罪したまはばいかにせむと、いまは其あまり氣高きが恐しくて、予は心細くも悲しくなりぬ。
あとへあとへと退りながら、
「御免なさい、御免なさい、こんだツから來ないから。あれ、うちへ歸して下さいよう。もうもう螢なんか取らないから、御免よ御免よ」とぞわびたりける。
姫が顔の色やゝ解けて、眉のび、唇 ゆるみぬ。肩寒げに垂れたる手を、たゆたげに胸のあたりに上げて、
「これかえ」
といひながら、つまみて、掌 に乘せたる、蒼きひかり裏すきて、眞白なる手の指のあひだの見えすくまで、太くも渠は痩せたるかな。
「上げませうか」
と呼びかけて、手をさしのべたる、袖の下に、わがからだ立寄る時、彼の君のぞくやうに俯向きたれば、はらはらと後毛溢れて二度ばかり冷かなる雫落ちぬ。胸に抱緊められたる時は、冷たさ骨髄にとほりつゝ、身は氷とや化すらむと、わが手足思はずふるひぬ。
「坊や、いくツだえ」
「なゝツ」 と呼吸の下に答へし身の、こはそもいかになることぞと、予は人心地もあらざりき。
「名は」とまた問ひつゞけぬ。
予は幽に答へ得たり。
「あゝ、みねさん、みイちやんだねえ」
「えゝ、」
かくて予を抱ける右の手に力を籠め、
「もうこんな處へ來るんぢやありません、母樣がお案じだらうに、はやくおかへり」といふはしに衝とすりぬけて身をひきぬ。
「入れものはあるかい」
と姫は此方に寄り添ひつゝ、予が手にさげたる螢籠の小さき口にあてがひて、彼の螢を入れむとして、輕くいきかけて吹き込みしが、空へそれて、ぱっと立ちて、梢を籠めて螢は飛びたり。
「あれ、」
と空を見上げたる、ぬれ髪は背にあふりて、兩の肩に亂れかゝりぬ。
「取つても可いかい、取つても可いんなら私がとらうや」
笹の葉一束結附けたる竹棹を持ちたれば、直に瀑におし浸して、空ざまに打掉るにぞ、小雨の如くはらはらと葉末を鳴して打散りたる、螢は岩陰にかくれ去りき。
やがて地藏の肩に見えぬ。枝のあたりをすいと飛びたり。また葉裏をぞつたひたる。小石の際よりぱつと立ちぬ。つと瀑を横ぎり行く。蒼き光の見えがくれに、姫は予が前後、また右左に附添ひつ。
予はたゞ螢を捕らむとばかり、棹を打ふり打ふりて足の浮くまであくがれたる、あたり忽ち月夜となりぬ。
唯見れば舊の廣野なりき。螢狩の人幾群か、わがつれも五七人、先刻には居たりし川も見ゆれど、何時の間にか歸りけむ、影一つもあらざりき。あたりはひろびろと果見えず、草茫々と生茂れる、野末には靄を籠めて、笠岡山朧氣なりし。
上の丘と下なる原とには、年長けてのち屡々行けど、瀑の音のみ聞きて過ぎつ。われのみならず、蓑谷は恐しき魔所なりとて、其一叢の森のなかは差覗く者もあらざるよし。優しく、貴く美しき姫のおもかげ瞳につきて、今もなつかしき心地ぞする。

